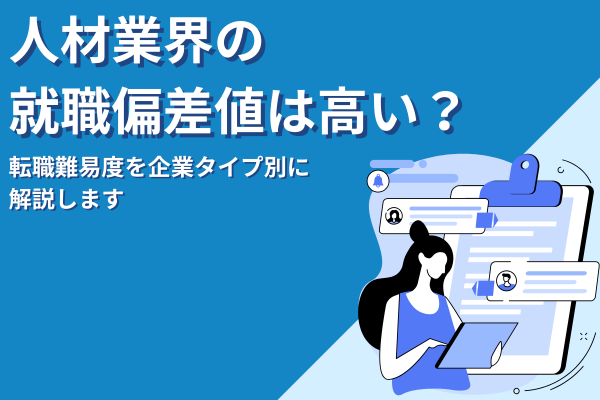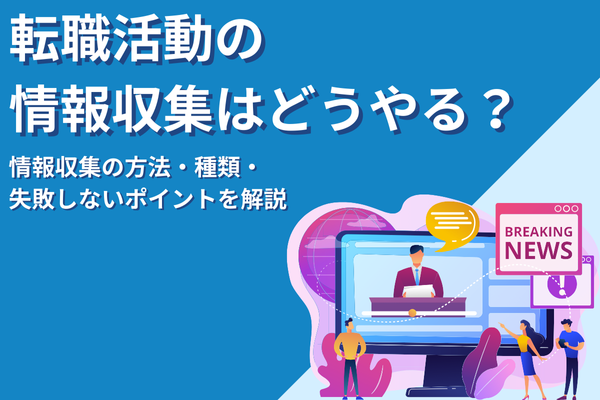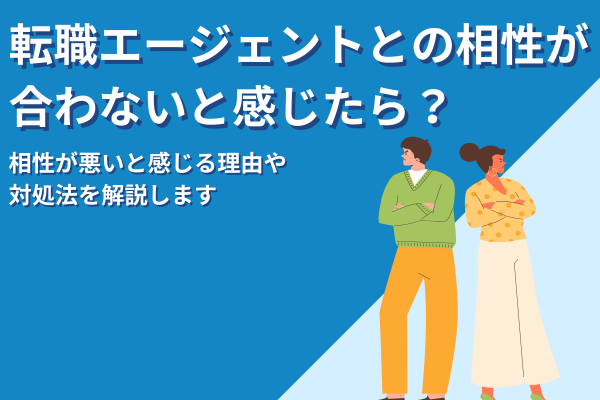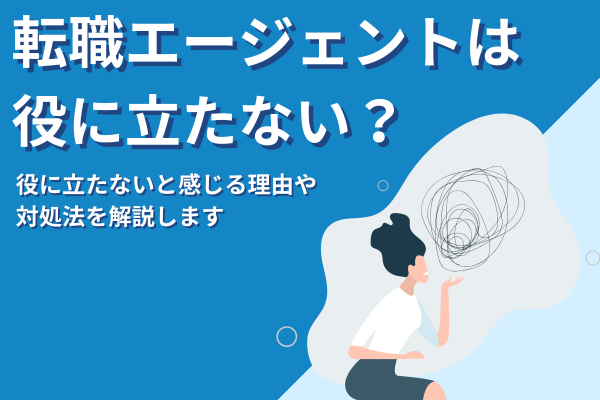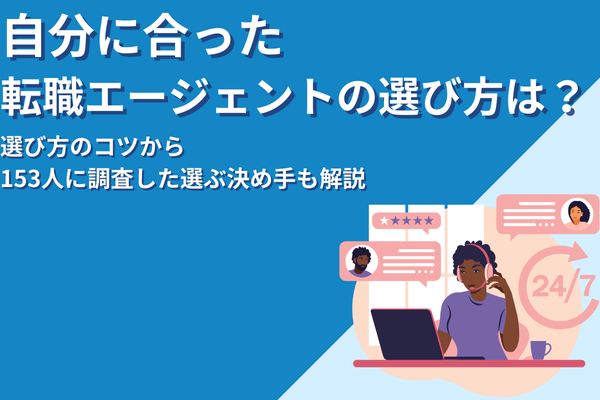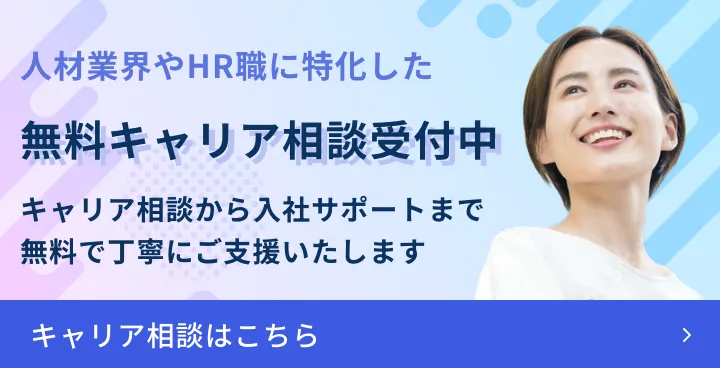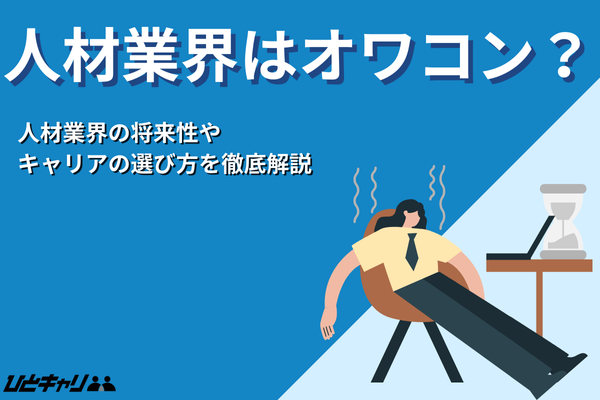
公開日: 2025.07.23
人材業界はオワコン?将来性を徹底解説
「人材業界ってもうオワコンなの?」
「やめとけって聞くけど、本当に将来性はないの?」
そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
確かに人材業界には過当競争やノルマの厳しさなど、ネガティブに語られがちな一面もありますが、社会貢献性が高く、スキルを積めばキャリアの選択肢が広がる業界です。
本記事では、人材業界が「オワコン」と言われる理由や実態、そして変化の激しい時代においてもチャンスを掴める人の特徴について詳しく解説します。
転職やキャリアの方向性に迷っている方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
また、人材業界特化の転職エージェント「ひとキャリ」では、人材業界への転職を目指す方に向けて、非公開求人やキャリア相談を通じて、一人ひとりに合った選択肢をご提案しています。
ぜひ一度、あなたの可能性を広げる第一歩としてご活用ください。
\人材業界の求人&面接対策/
目次
なぜ「人材業界はオワコン」と言われるのか?考えられる理由

人材業界は「オワコン」と耳にすることがありますが、実際にはどのような背景があるのでしょうか。
ここでは、人材業界がネガティブに捉えられやすい主な理由を4つの視点から整理して解説します。
人材業界は企業の競争が激しい
人材業界が「オワコン」と言われる理由のひとつに、企業間の過当競争があります。
参入障壁の低さや市場拡大によってプレイヤーが急増し、他社との差別化が非常に難しくなっているためです。
競争の激しさを示すポイントは、以下が挙げられます。
- 民営職業紹介事業所は令和5年度時点で約3万件(平成元年の約10倍)
- 初期コストが低く、参入しやすいため新規事業者が増加
- 類似したサービスを提供する会社が多く、差別化が難しい
- 求職者や企業のニーズが多様化し、専門知識や経験が必要
- 業界・職種に特化したサービスや明確なブランディングが求められる
事業者数の増加とサービスの類似化により、単なる人材紹介では生き残れない時代に入りつつあるといえるでしょう。
人材業界は社員が疲弊しやすい
人材業界では、日々の業務において精神的な負担を感じる社員が少なくありません。
成果報酬型のビジネスモデルが主流であり、短期的な数字を追い求めるプレッシャーが強いためです。
社員が疲弊しやすい背景には、以下のような実情があります。
- 成果報酬制が多く、早期の成約が強く求められる
- 収益優先のあまり、求職者の希望が軽視されることがある
- 求職者を「売り物」のように扱っていると感じ、罪悪感を抱く
- トラブルの多い職場や人間関係の問題に触れる機会が多く、精神的に消耗しやすい
こうした構造的なストレス要因が積み重なり、離職やメンタル不調につながりやすい業界といえるでしょう。
人材業界は長時間労働になりやすい
人材業界では、長時間労働が常態化しやすく、働き方に悩む社員も多いのが現状です。
求職者と企業の双方に対応する必要があり、勤務時間が不規則になりがちで、ワークライフバランスを保つのが難しくなる傾向があります。
長時間労働につながりやすい状況は、以下のとおりです。
- 求職者・企業の都合に合わせるため、勤務時間が不規則になる
- 夜間・休日の面談や急な案件対応が発生しやすい
- 平日は社内業務や企業訪問が多く、面談は夕方以降に集中しがち
- 内定・入社直前は調整業務が立て込み、定時退社が困難になる
- プライベートの時間が削られやすく、私生活との両立にストレスを感じる人が多い
こうした働き方が続くことで、心身ともに疲れを感じやすくなり、業界への定着を難しくしている一因とも考えられます。
企業が技術の進歩に対応できない
人材業界が「オワコン」と言われる背景には、企業側の技術対応の遅れが影響しています。
求職者側は急速に進化するITサービスに慣れつつある一方で、求人企業の多くが従来型の採用スタイルから脱却できていません。
技術対応の遅れによって生じる課題は、以下のとおりです。
- 採用活動がプラットフォームやAIによるマッチングに移行している
- 求職者は副業アプリ、ビジネスSNS、動画面接などを使いこなしている
- 一方で、従来型の人材サービスに依存する企業が多い
- 応募から条件交渉までの効率化に乗り遅れると、求職者との接点が減少
- AIマッチングや選考ツールを活用しない企業は採用競争で不利になる
- テクノロジーの活用と倫理的な情報管理の両立も今後の課題
変化に追いつけない企業が取り残されることで、人材業界全体の印象が古くさく見え、オワコンと呼ばれる一因になっています。
こちらも併せてチェック!
人材業界がやめとけと言われる理由を徹底解説
人材業界はこれからどうなる?将来性と社会的な必要性
ここでは、市場データや人口動態の変化をもとに、人材業界の将来性と今後求められる役割について解説します。
市場規模は右肩上がりで拡大傾向にある
人材業界は「オワコン」と言われがちですが、実際には市場規模が年々拡大しており、今後も成長が見込まれています。
企業のDX推進や人手不足の影響により、特にデジタル人材へのニーズが高まっているためです。
市場の成長を示す具体的なデータは、以下が挙げられます。
- 2023年度の人材関連ビジネス市場は約9兆7,156億円(前年比6.3%増)
- デジタル人材向け市場は1兆3,615億円(前年比9.1%増)に成長
- ホワイトカラー職種の人材紹介市場は4,110億円(前年比17.1%増)
- フリーランスデジタル人材とのマッチングサービスの需要も拡大中
人材業界は単なる紹介・派遣にとどまらず、デジタル技術との融合によって今後も進化し続ける可能性の高い分野だといえるでしょう。
参考:株式会社矢野経済研究所「人材ビジネス市場に関する調査(2024年)」、「デジタル人材を対象とした人材サービス市場に関する調査を実施(2025年)」
少子高齢化により人材業界の社会的ニーズはさらに高まる
日本社会が直面する少子高齢化により、人材業界の社会的な役割は今後さらに重要性を増すと考えられます。
生産年齢人口の減少が続く中、労働力不足の解消には、適切な人材の確保と配置を担う専門的な支援が不可欠です。
人材業界への期待が高まる背景は、以下が挙げられます。
- 生産年齢人口が減少し、労働力不足が慢性化
- 医療・介護・情報通信分野で就業者が増加し、人手不足が深刻化
- 女性・高齢者の労働参加や教育を通じた労働の質向上が求められる
- 働き手の確保と最適配置を支援する専門機能として人材業界が注目されている
- マッチング精度の高さが、経済活動の持続性を左右する段階に入っている
構造的な人口減少のなかで、雇用の量と質を確保する手段として、人材業界の機能と専門性は今後ますます求められていくでしょう。
\人材業界の求人&面接対策/
こちらも併せてチェック!
人材業界の現状の課題と今後の見通しを解説
「人材業界はオワコン」と言い切れない魅力とは?
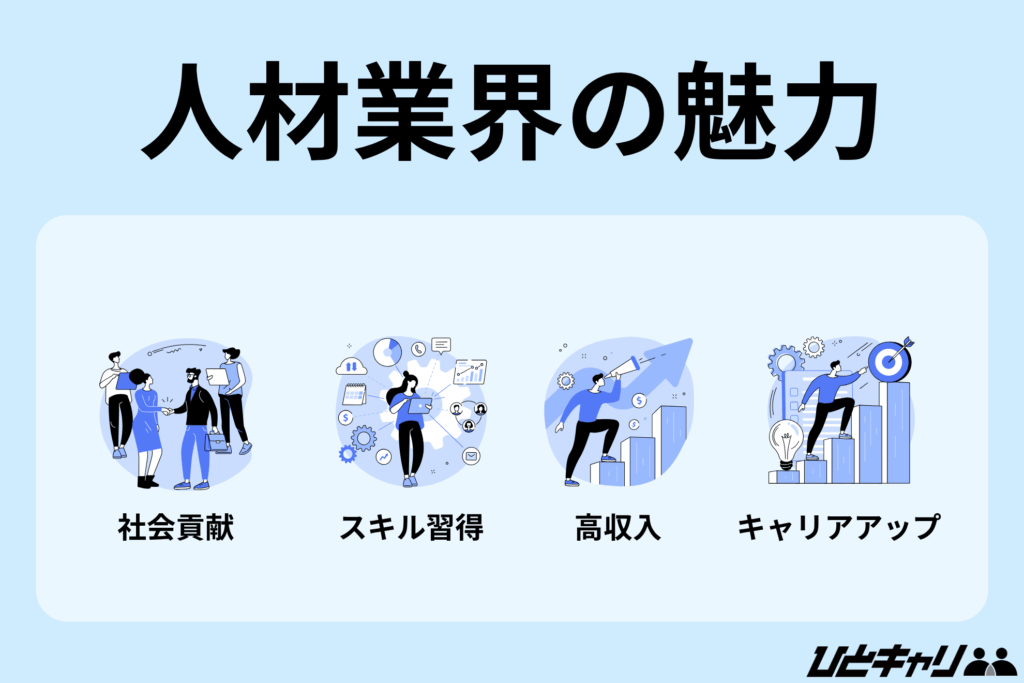
人材業界には競争の激しさや労働環境の厳しさといった課題があるのは事実ですが、それでも働くことにやりがいや価値を感じている人が多いです。
ここでは、人材業界ならではの魅力や成長機会について、4つの視点からご紹介します。
人と企業の架け橋として社会に貢献できる
人材業界は、個人と企業の間に立って橋渡しをすることで、社会に価値を提供できる仕事です。
働く人にとっては「人生の転機」となる場面に寄り添い、企業にとっては「成長の原動力」となる人材を届ける存在として、両者の未来を支える役割を担います。
たとえば、長く転職に悩んでいた求職者が、自分らしく働ける職場に出会い、表情が明るく変わっていく姿に立ち会う場面があります。
また、採用に課題を抱えていた企業に対して、マッチ度の高い人材を紹介した結果、経営課題の解決に貢献できたという声をいただくこともあるでしょう。
人と企業をつなぐというシンプルでありながら奥深い仕事には、数字では測れないやりがいが確かに存在しています。
社会貢献を実感しながら働きたい人にとって、人材業界は大きな可能性を持つフィールドです。
キャリア支援のスキルが身につく
人材業界で働くことで、キャリア支援に関する実践的なスキルが自然と身につきます。
求職者との面談や企業への提案を通じて、多様な業界知識や課題解決力を磨く機会が日常的にあるためです。
スキルや視野が広がる具体的な場面は、以下が挙げられます。
- 面談や提案を通じて営業力や問題解決力が身につく
- 多様な業界・職種の知識を実務の中で習得
- 転職事例を通じて人の可能性に気づく視点が育つ
- 自身のキャリアを考えるうえでも思考の柔軟性が広がる
- 課題対応の経験が重なり、実感できる成長につながる
人材業界での実務経験は、単なるビジネススキルにとどまらず、自分自身のキャリア形成にプラスとなるでしょう。
成果が出れば若くして高収入も狙える
人材業界では、成果を出せば年齢に関係なく高収入を得られ、若いうちから経済的な成功を目指せます。
人材紹介や派遣営業では、成果報酬型の給与体系を採用している企業が多く、自身の成績に応じてインセンティブが支給される仕組みが整っているためです。
たとえば、成約1件につき数十万円から数百万円のインセンティブが発生するケースもあり、20代後半で年収1,000万円を超える人も珍しくありません。
頑張りが数字に反映されるため、日々の営業活動にも張り合いが出やすく、成果を出すことでキャリアアップと経済的安定の両方を手に入れられます。
人材業界は年功序列に縛られず、成果次第で若くして収入を大きく伸ばせるチャンスのある業界です。
自分の力で稼ぎたいと考える人には、魅力的なフィールドといえるでしょう。
\人材業界の高年収求人&面接対策/
人材業界での経験がキャリアアップに直結する
人材業界での経験は、自身のキャリアアップにつながりやすい実践的な強みになります。
人材業務を通じて培われる業界知識・人脈・提案スキルが、他業種や他職種でも高く評価されるためです。
たとえば、営業職やキャリアアドバイザーとして成果を積み上げ、20代でマネジメント職に就く人も少なくありません。
また、日々多様な業界・企業と関わる中で、「この分野でもっと深く関わってみたい」と思い、事業会社の人事やマーケティング職に転職するケースもあります。
人材業界で培ったコミュニケーション力や課題解決力は、コンサルタントや企画職など他領域にも応用しやすく、実力次第でキャリアの選択肢が一気に広がるでしょう。
\人材業界のキャリアアップ支援/
こちらも併せてチェック!
人材業界の魅力について徹底解説
人材業界に向いている人の特徴
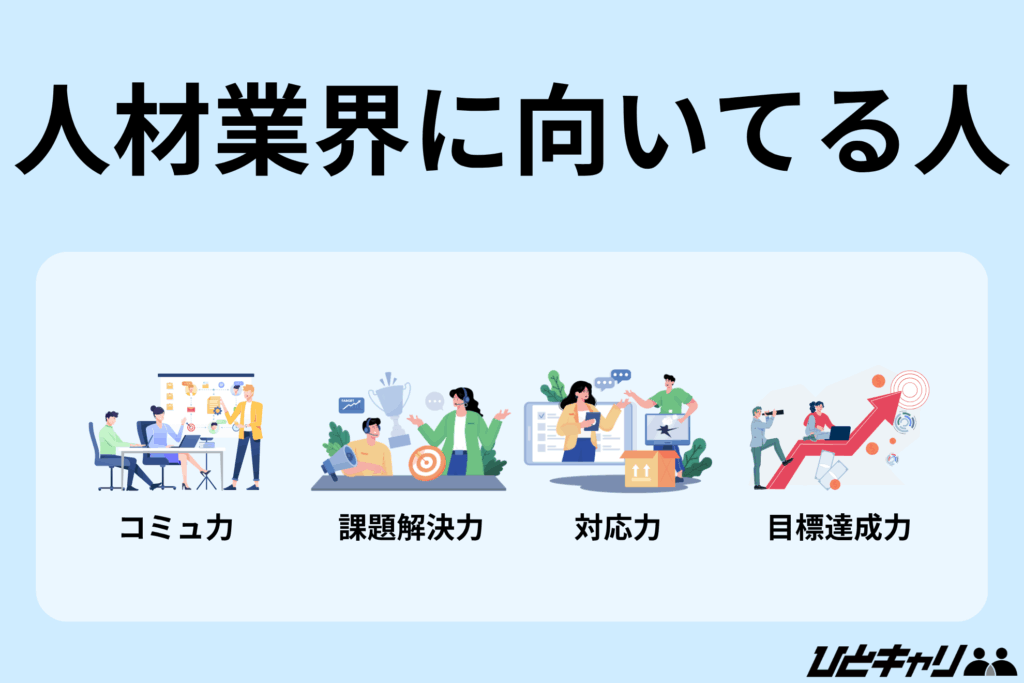
人材業界は、企業と求職者の間に立ち、それぞれの課題やニーズに応える重要な役割を担う仕事です。
ここでは、人材業界で活躍しやすい人に共通する特徴を4つの視点からご紹介します。
コミュニケーション能力が高い人
人材業界では、コミュニケーション能力が高い人が特に活躍しやすい傾向にあります。
求職者や企業担当者と信頼関係を築き、ニーズや本音を引き出していくためには、丁寧なヒアリングと的確な伝達が不可欠です。
具体的には、以下が挙げられます。
- 求職者・企業双方との信頼関係を築く対話力
- ニーズや課題を引き出すヒアリングスキル
- 専門的な情報をわかりやすく説明する力
- 職種・条件・背景に応じた柔軟な伝え方
- 年齢や立場の異なる相手との円滑な関係構築
- 採用後も続く継続的なフォロー力
人材業界では「話す力」だけでなく、「聞く力」や「伝え分ける力」が大切です。
多様な人と信頼関係を築ける人こそ、この仕事に向いているといえるでしょう。
課題の本質を見抜き解決できる人
人材業界では、表面的な要望にとらわれず、課題の本質を見抜いて提案できる人が活躍します。
背景にある真のニーズを汲み取ってこそ、最適なマッチングや信頼ある関係構築につながるためです。
求められる視点やスキルは、以下が挙げれます。
- 表面的な要望の背後にある根本課題を見極める力
- 「なぜ今、採用したいのか」など背景まで踏み込んでヒアリング力
- 組織体制や業務内容にまで目を向けた提案ができる
- 論理的に情報を整理し、企業に納得感を与える提案力
- 課題解決型の営業スタイルで信頼を築くスキル
問題の本質を捉え、的確な解決策を提示できる人は、企業・求職者の双方から信頼され、人材業界でも重宝される存在となるでしょう。
柔軟な発想で変化に対応できる人
変化の激しい人材業界では、柔軟な思考で状況に応じた対応ができる人が向いています。
市場ニーズや働き方のトレンドは常に変化しており、同じ方法が通用し続けるとは限りません。
固定観念にとらわれず、新しい視点で課題を捉え直せる人は、より良いマッチングや提案を実現できます。
求められる思考や行動の具体例は、以下のとおりです。
- 採用市場や働き方のトレンドを敏感にキャッチする
- 一見ミスマッチなケースにも可能性を見出す柔軟な視点がある
- 固定観念にとらわれず、課題を多角的に分析できる
- 既存のやり方に依存せず、前例にない提案を形にできる
- 変化を前向きに楽しみ、成長のチャンスと捉えられる
変化を受け入れて発想を切り替えられる人は、人材業界での活躍の幅を自然と広げられるでしょう。
目標達成にやりがいを感じる人
人材業界では、目標に向かって粘り強く取り組める人が活躍しやすい傾向にあります。
成果が明確に数字で評価される業界であるため、プレッシャーもある一方で、達成感ややりがいを強く感じやすい環境のためです。
業務の中で求められる適性や行動は、以下が挙げられます。
- 数字や納期のプレッシャーに日常的に向き合う
- 成果が数字で明確に評価される
- 気持ちを切り替え、次に集中できる対応力
- 追い込み期でも冷静に判断し、成果を積み上げる力
- 数字に前向きに向き合えるストレス耐性
目標を負担ではなくモチベーションと捉えられる人にとって、人材業界は努力が報われやすいフィールドといえるでしょう。
\人材業界の求人&面接対策/
転職したいけど、どのエージェントがいいか分からない方はこちらをチェック!
人材業界の転職エージェント14選
人材業界に向いていない人の特徴
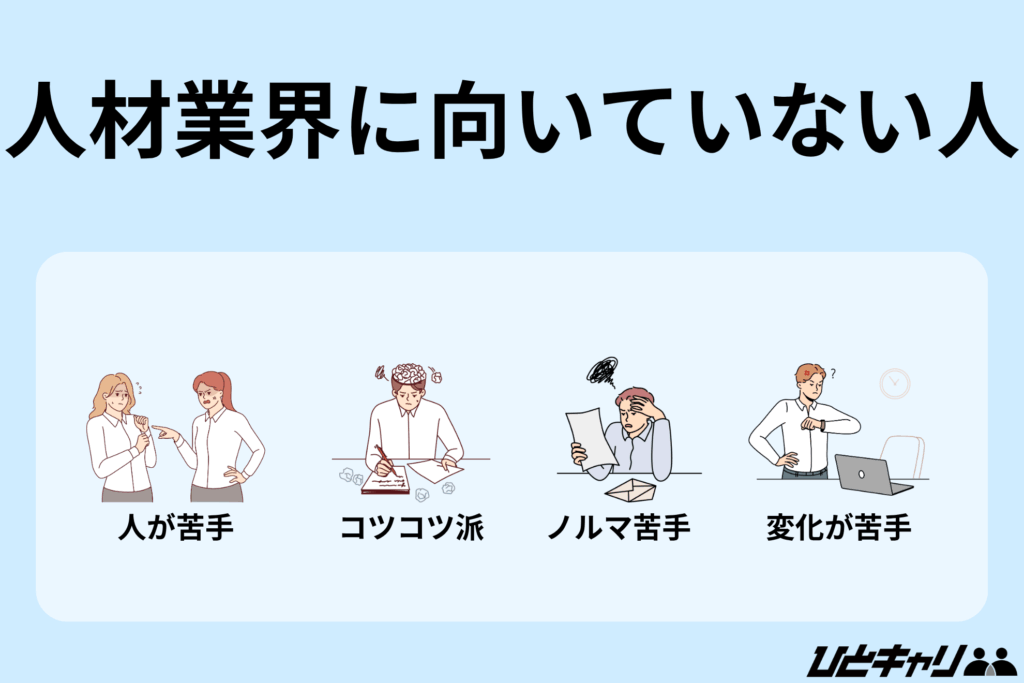
人材業界は、スピード感のある対応力やコミュニケーション能力が重視される環境です。
ここでは、人材業界で働く際に「ミスマッチになりやすいタイプ」の特徴を解説します。
人と関わるのが苦手な人
人と関わることに強い苦手意識がある人は、人材業界の業務にストレスを感じやすいです。
人材業界は、業務の大半が対人対応で占められており、人とのやり取りが避けられません。
日常的に求められる対人対応は、以下のとおりです。
- 初対面の相手と会話・面談・交渉を繰り返す
- 一日で複数人と電話・メール・オンライン面談などをこなす
- 相手の本音を引き出すために、深掘りする質問ややや踏み込んだ対話が必要
- 丁寧かつ粘り強いやり取りが求められる場面が多い
対人関係が中心となる環境では、コミュニケーションに強い苦手意識があると日々の業務が負担になりやすく、長く働くうえで消耗してしまう可能性が高いでしょう。
安定した環境でコツコツ働きたい人
静かにコツコツと働きたい人にとって、人材業界はミスマッチになりやすい業界です。
人材業界では、求職者や企業とのやり取りが日常的に発生し、状況に応じた対人対応や判断が求められます。
業界とのギャップが生じやすい要素は、以下のとおりです。
- 求職者・企業と連日やり取りが発生する
- 一人で黙々と進める作業は少なく、変化のある業務が多い
- 対応スピードや臨機応変な判断力が求められる
- 高い対人スキルや提案力が評価される職種が中心
ルーティンワークや静かな環境を重視する人は、人材業界のスピード感や対人中心の働き方に負担を感じやすいでしょう。
ノルマや数字に強い抵抗がある人
数字に強いストレスを感じる人や、プレッシャーに弱い人は、人材業界では疲弊しやすい傾向があります。
人材業界は成果主義の色が濃く、売上や成約件数などの数値で評価される環境が一般的なためです。
数字に対する抵抗感が課題となりやすい要素は、以下が挙げられます。
- 月間・四半期ごとに目標達成が求められる
- 売上や成約件数などの数値で厳しく評価される
- 成績が社内で共有され、比較されるケースもある
- ノルマ未達時には、上司からの指導や評価の低下につながる
- 失敗を引きずりやすい人は、メンタル面で負担を感じやすい
数字に対して強い抵抗感がある場合、人材業界の評価制度や日常のプレッシャーがストレス要因になりやすいでしょう。
変化にストレスを感じやすい人
「いつも通り」の環境を好む人にとっては、人材業界の変化の多さが大きなストレスになる可能性があります。
人材業界では、日々新しい求職者や企業とのやり取りが発生し、市場やニーズの変化に応じて対応を変えていく必要があるためです。
変化に対応できないと負担になりやすい場面は、以下が挙げられます。
- 求職者や企業との関わりが毎日変わる
- クライアントのニーズや市場動向が流動的
- 突発的な予定変更・対応依頼が頻繁に発生
- 状況に応じて判断や方針を切り替える場面が多い
- 決まった手順・ルーティンを重視する人には負担が大きい
変化を前向きに受け入れられないと、ストレスや疲労が蓄積しやすくなるでしょう。
臨機応変な対応が苦手な人にとっては、人材業界は慎重に見極めたい業界のひとつです。
人材業界の職種と仕事内容
ここでは、人材業界で代表的な4つの職種について、その仕事内容や役割の違いを詳しく解説します。
人材派遣
人材派遣は、企業と働き手をつなぐ柔軟な雇用の形として、専門的な調整力が求められるビジネスです。
派遣スタッフは派遣会社に雇用されながら、実際の業務は派遣先企業でおこないます。
人材派遣の仕組みと現場の実務は、以下のようになっています。
- 派遣スタッフと派遣会社の間には「雇用関係」がある
- 実際の勤務先である派遣先企業とは「指揮命令関係」が成立する
- 給与の支払いは派遣会社が行い、労務管理も派遣会社が担当
- 派遣できる職種や期間は「労働者派遣法」により制限されている
- 派遣スタッフのスキルや希望条件に合った職場への配置が求められる
- 企業側のニーズも踏まえた調整力が成果に直結する
人材派遣は、法制度の理解やマッチング精度が求められる分野です。
双方にとって満足度の高い派遣を実現するためには、高度なヒアリング力と調整力が欠かせません。
こちらも併せてチェック!
人材派遣会社とは?仕事内容や年収を徹底解説
人材紹介
人材紹介は、企業と求職者の双方に寄り添い、正社員採用を実現するための仲介役を担う仕事です。
採用が成立した際に報酬(紹介料)が発生する成功報酬型のビジネスモデルであるため、双方にとってミスマッチのない丁寧な対応が求められます。
人材紹介の主な業務は、以下のとおりです。
| 担当領域 | 担当者 | 主な業務内容 |
|---|---|---|
| 企業対応 | リクルーティングアドバイザー(RA) | ・採用企業と契約を結び ・求める人物像やスキルをヒアリング ・求人票の作成 |
| 求職者対応 | キャリアアドバイザー (CA) | ・キャリア相談 ・求人紹介 ・面接対策 ・入社日調整 ・内定後フォローなど |
| 担当体制 | 企業によって異なる | RA・CAを分業する体制と、1人で両方を兼任する体制がある |
| 報酬発生 タイミング | 共通 | 求職者の入社が決定した時点で企業から紹介料を受け取る(成功報酬型) |
正確なヒアリング力や信頼関係の構築力が求められるため、丁寧な対応ができる人ほど成果を上げやすい分野といえるでしょう。
\人材紹介の求人&面接対策/
こちらも併せてチェック!
人材紹介とは?総合型と特化型を徹底解説
人事コンサルティング
人事コンサルティングは企業の「ヒト」に関わるあらゆる課題に対して、分析・提案・実行支援をおこなう重要なポジションです。
戦略的かつ実行可能な人事施策を立案・提案し、企業を支える人事コンサルタントの存在が注目されています。
人事コンサルティングの主な業務は、以下のとおりです。
| 領域 | 内容 |
|---|---|
| 採用支援 | ・新卒・中途採用計画の立案 ・母集団形成 ・面接設計のアドバイス |
| 人材育成 | ・研修制度の企画・実施 ・評価制度との連動支援 |
| 組織課題の分析 | 離職率や人材定着率などをもとに現状を可視化し、課題を特定 |
| 制度設計 | 人事評価制度・等級制度・報酬制度などの設計と導入支援 |
| プロジェクト運営 | 一社ごとにチームを組み、長期的に関係を築きながら運用を支援 |
| キャリア支援 (人材コンサルタント) | 求職者の相談対応、キャリア設計の提案など「個人支援」に特化する場合もあり |
人材確保の難しさが増す中、その専門性と需要は今後ますます高まっていくでしょう。
求人広告
求人広告は、企業の魅力を言語化し、ターゲットとなる求職者に届くよう工夫するクリエイティブな仕事です。
企業と転職者の最初の接点をつくる、重要な役割を担っています。
求人広告の仕事内容と媒体の種類は、以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な業務 | ・企業への営業・求める人物像のヒアリング ・求人広告の企画 ・原稿作成 ・掲載後の効果測定や改善提案 |
| 有料媒体例 | リクナビNEXT、マイナビ転職、エン転職など |
| 無料媒体例 | Indeed、Googleしごと検索(Google for Jobs)など |
| 紙媒体の特徴 | 地域密着型例:新聞折込・駅設置のフリーペーパーなど |
| Web媒体の特徴 | 全国対応・検索性が高い例:特集や勤務地軸の絞り込みが可能 |
求人が埋まったときの達成感は大きく、企業の採用活動を陰から支える重要な役割を担っています。
人材業界で「オワコン」にならない働き方とは?
ここでは、人材業界で時代に左右されずに活躍し続けるための働き方や考え方について、3つの視点から解説します。
自分に合った職種・領域を選ぶ
人材業界で長く活躍するには、自分に合った職種や領域を選ぶことが重要です。
適性や価値観と合致した選択をすれば、変化の激しい業界でもやりがいを持って働き続けられます。
具体的な行動・視点は以下のとおりです。
| 行動・視点 | 内容 |
|---|---|
| 自己分析の実施 | 過去の経験を時系列で整理し、成功体験や苦手だった場面を振り返る |
| 価値観・特性の明確化 | どんなときにやりがいを感じたか、どういう環境で力を発揮しやすいかを言語化する |
| 適性との照合 | 自分の特性と、希望職種に求められるスキル・性格傾向を比較する |
| 客観的な意見の活用 | 信頼できる第三者からのフィードバックで、思い込みを避ける |
| 汎用スキルの育成 | 自己分析を通じて身につく「情報収集力」「分析力」「言語化力」は、人材業界での提案活動でも活かせる |
丁寧な自己分析と客観的視点をもとに選択すると、たとえ業界が変化してもオワコン化しない強い働き方が実現できます。
業界分析で「自分に合う環境か」を見極める
人材業界で後悔のない選択をするためには、自己理解とあわせて業界分析をおこない「自分に合う環境かどうか」を客観的に見極めることが重要です。
十分な情報を得ずに入社すると、仕事内容や社風とのギャップに苦しむケースも少なくありません。
具体的な判断ポイントは、以下のとおりです。
- 自己分析で明らかにした価値観や特性と、業界の特性がマッチしているか確認する
- 上司との距離感、評価制度、働き方の柔軟性など、社内環境との相性を確認する
- OB訪問・口コミ・会社説明会・求人票の文面などから、現場のリアルな声を収集する
- 今後の業界動向やキャリアの広がりも含めて、成長できる環境かを見極める
業界分析を通じて、納得のいく選択を目指しましょう。
変化に強いスキルを磨き、キャリアアップにつなげる
人材業界で長く活躍していくには、変化に柔軟に対応できるスキルを身につけておくのをおすすめします。
働き方の多様化やデジタル化の加速により、企業や求職者のニーズも日々変化しているためです。
具体的に求められるスキルや行動例は、以下が挙げられます。
- 想定外の状況でも前向きに捉え、解決策を見出す力
- Zoom、Slack、Salesforceなどの業務ツールを積極的に習得・活用する
- 市場トレンドやITスキルの変化を自ら学び続ける
- クライアントや求職者の急な方針転換にも冷静に対応する
- 複数案件を並行して進めながら、状況に応じて優先順位を調整する
今後ますます変化が加速する人材業界で活躍するには、現状維持に甘んじず、常に新しいスキルを学び、変化に強い自分を育てていくといいでしょう。
人材業界はオワコンじゃない!どう働くかでキャリアの可能性は広がる
人材業界は「オワコン」と言われることもありますが、実際には社会や企業の変化にあわせて進化を続けている分野です。
従来のやり方に固執するのではなく、自ら学び、柔軟に動ける人にとっては大きなチャンスが広がっています。
これからの人材業界に求められるのは、情報をつなぐだけの存在ではなく、「人と企業の本質的なマッチングを支援する力」です。
人材業界でのキャリアを前向きに検討している方は、業界の動向や自分の特性を踏まえたうえで、最適なフィールドを見つけてください。
また、人材業界特化の転職エージェント「ひとキャリ」では、人材業界への転職を目指す方に向けて、非公開求人やキャリア相談を通じて、一人ひとりに合った選択肢をご提案しています。
ぜひ一度、あなたの可能性を広げる第一歩としてご活用ください。
\人材業界の求人&面接対策/