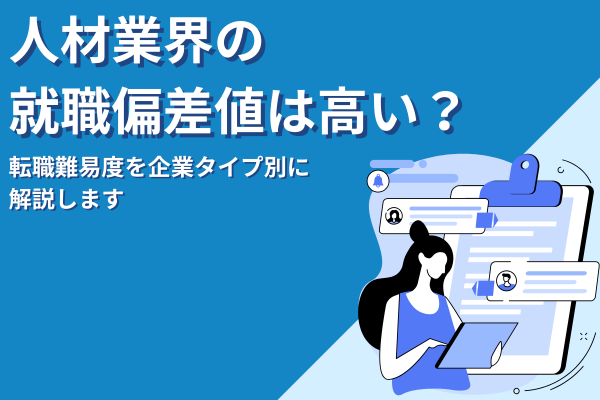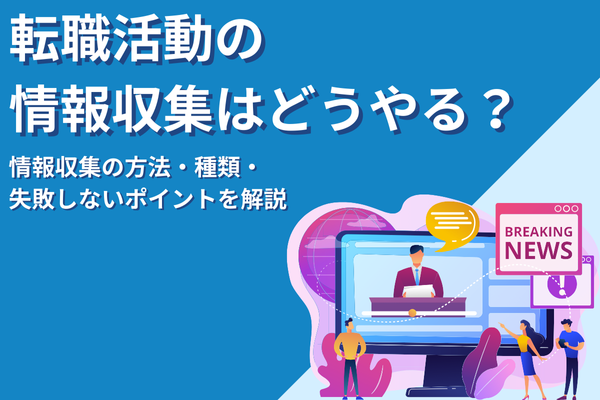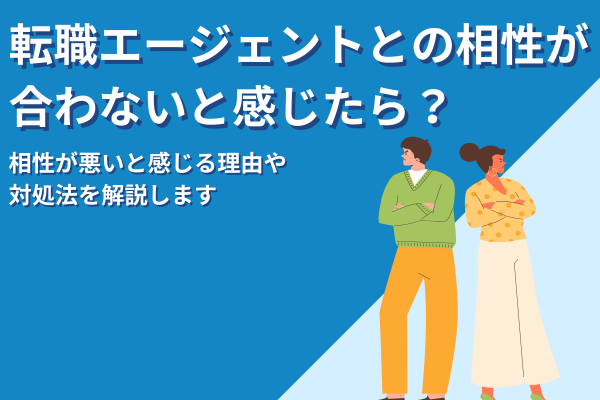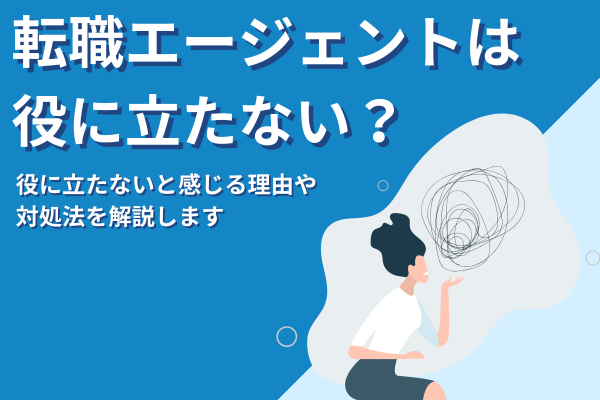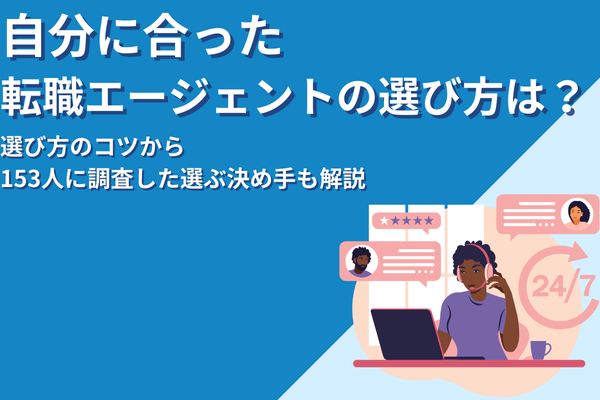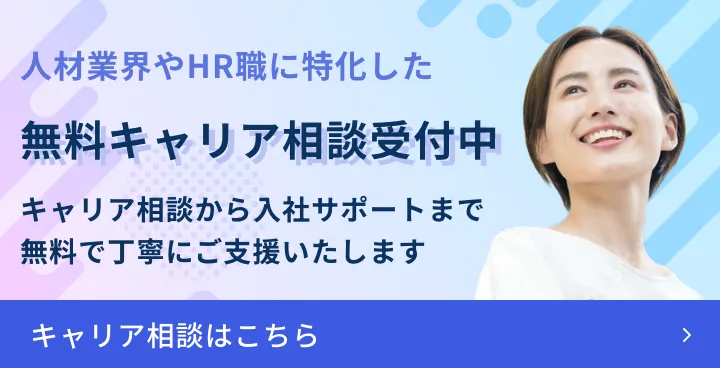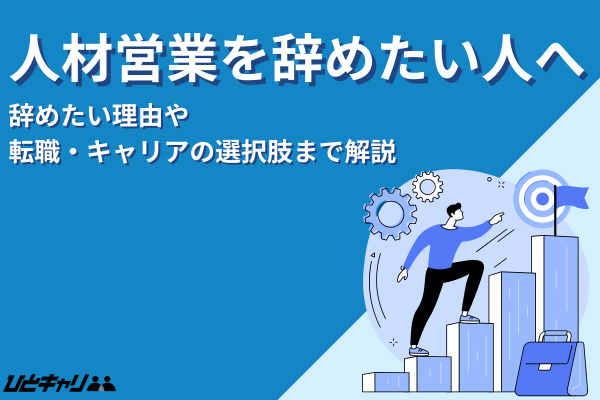
公開日: 2025.09.24
人材営業を辞めたい人へ|理由から転職・キャリアの選択肢まで解説
人材営業は、企業と求職者をつなぐ社会的意義の高い仕事ですが、その一方で強いプレッシャーや多忙さから「もう辞めたい」と感じる人も少なくありません。
厳しいノルマやKPI、長時間労働、私生活との両立の難しさなど、現場で直面する悩みは多岐にわたります。
では、人材営業を辞めたいと感じたときにどう行動すべきでしょうか。
この記事では、人材営業を辞めたい理由から離職率の実態、辞める前にできる工夫、転職先の選択肢、さらに営業で培ったスキルの活かし方まで幅広く解説します。
人材営業に悩んでいる方や、転職を検討している方はぜひ参考にしてください。
目次
人材営業を「辞めたい」と感じる主な理由
人材営業の仕事はやりがいがある一方で、厳しい環境に直面することも少なくありません。
ここでは、代表的な理由を詳しく解説します。
厳しいノルマやKPIで強いプレッシャーを感じる
人材営業を「辞めたい」と思う大きな理由の一つに、厳しいノルマやKPIによるプレッシャーが挙げられます。
営業職は成果主義で、数値管理が強く求められるため精神的な負担が大きくなりやすいです。
プレッシャーを感じる例
- 応募者数や顧客対応件数など、細かいKPIが設定される
- 目標達成のために長時間労働が必要になることも多い
- 高すぎる数値目標に理不尽さを感じやすい
- 達成できないと退職や転職を考えるきっかけになる
厳しい数値管理は、辞めたい理由の代表例ですが、状況を見極め、自分に合う会社やキャリアを考えるといいでしょう。
長時間労働や休日対応で私生活が犠牲になる
人材営業は、長時間労働や休日対応によって私生活が犠牲になる場合があります。
人材業界の営業職は、採用企業や求職者への対応が中心であり、勤務時間が不規則になりやすいためです。
業務が多く、会社によっては休日出勤を求められるケースも少なくありません。
私生活が犠牲になる具体例
- 業務量が多く労働時間が長くなる
- 休日出勤を求められる会社もある
- 自分の時間が取れずストレスがたまる
- 土日休みの会社へ転職を考える人も多い
人材業界での営業はやりがいがある一方で、私生活を犠牲にする働き方になりやすいのも事実です。
キャリアを長期的に考えるなら、自分に合った労働環境の会社への転職を検討しましょう。
業務量の多さで常にキャパオーバーになる
人材営業の仕事は業務量が多く、常にキャパオーバーを感じることが辞めたい理由として挙げられます。
人材業界は人手不足の企業が多いため、担当者一人に営業・採用・求職者対応など幅広い業務が集中しやすいためです。
長時間労働や休日対応が増え、仕事と私生活のバランスを崩すケースが少なくありません。
業務過多の具体例
- 夜間に事務作業や転職希望者の対応が続く
- 「お客様第一」で動くため労働時間が延びやすい
- 給与が労働量に見合わず、不満や疲労がたまりやすい
長期的なキャリアを考えるなら、自分のペースで働ける会社や職種への転職を検討するのも選択肢の一つです。
入社前のイメージと現実のギャップに落胆する
人材業界の営業は「入社前に思っていた理想」と「実際の仕事の現実」のギャップが大きく、辞めたい理由になりやすいです。
転職希望者のキャリア支援にやりがいを感じて入社しても、実際にはノルマやKPI達成を優先しなければならず、理想と現実の違いに直面するでしょう。
ギャップを感じやすい場面
- 「一人ひとりに寄り添いたい」と入社したが、数十人を同時に担当することが多い
- 時間不足で十分な対応ができず、流れ作業のように感じる
- KPI達成を優先し、適性に合わない求人を紹介することもある
入社前の期待と現実の違いは大きく、モチベーション低下や退職の理由になりがちです。
ズレに直面するとやりがいを見失いやすいため、転職やキャリアチェンジを検討するきっかけとなるでしょう。
人材営業を辞める人は多い?離職率の実態
人材営業は辞める人も多いですが、新しく入る人も多いため、業界全体としては流動性が高いのが特徴です。
厚生労働省の調査によると、人材営業が属する「サービス業(他に分類されないもの)」は、一般労働者の入職率が19.4%、離職率が19.0%と、出入りが激しいもののほぼ同じ水準になっています。
つまり、辞める人が多い一方で、それを上回るほどの新規入職者がいるため、常に人の動きが活発な業界といえるでしょう。
統計データを比較すると以下のとおりです。
| 区分 | 入職率 | 離職率 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 全産業平均 | 14.8% | 14.2% | わずかに入職超過 |
| サービス業 (他に分類されないもの) 一般労働者 | 19.4% | 19.0% | 出入りが激しいがほぼ同じ水準 |
| サービス業 (他に分類されないもの) パートタイム | 27.6% | 23.8% | 回転が非常に速い |
人材営業は「辞める人が多い=厳しい仕事」という一面がありますが、同時に新しい人材が次々と入ってくる活発な業界でもあります。
キャリアアップを目指すなら、この高い流動性を前向きに捉え、自分に合った会社や働き方を選ぶのが重要です。
人材営業を辞める前に試してみたい対処法
人材営業の仕事に悩み、辞めたいと思ったときでも、いきなり退職を決断する必要はありません。
ここでは、人材営業を辞める前に試してみたい具体的な対処法を紹介します。
辞めたい理由を具体的に言語化する
人材営業を辞めたいと感じたときは、まず「理由」を具体的に言語化することが重要です。
理由をあいまいにしたまま退職や転職を進めると、業界や会社を変えても同じ仕事の悩みやストレスに直面する可能性があります。
辞める前に整理すべきポイントは、以下のとおりです。
- 不満の根本(ノルマ・労働時間など)を深掘りする
- 「絶対に避けたい条件」と「譲れない条件」を書き出す
- 転職後のキャリア形成に活かせる強み・経験も合わせて整理する
辞めたい理由を言語化しておくと、転職活動で自分に合う企業を選びやすくなり、キャリアの成功につながります。
辞めずに続けられる条件を考える
人材営業を辞めたいと感じたときでも、必ずしも退職が唯一の選択肢とは限りません。
自分がどの条件なら仕事を続けられるのかを整理することが大切です。
辞めたい理由をストレスで片づけず、会社のノルマや営業手法など具体的な要因に分ければ、改善策が見つかります。
続けられる条件の整理方法は、以下のとおりです。
- 無理なノルマや過度な残業がなければ続けられるのか
- 扱う商材や提案スタイルが自分に合えば前向きに取り組めるのか
- サポート体制や上司の対応が改善されれば続けやすいのか
辞めたい気持ちを「辞めるしかない理由」としてではなく、「環境を変えれば続けられる条件」として見直してみましょう。
人材業界の仕事は企業や営業スタイルによって大きな違いがあるため、転職を決断する前に続けられる可能性を探ってみる価値があります。
行動量や目標の見直しをおこなう
人材営業の仕事で「辞めたい」と感じるときは、行動量や目標を柔軟に見直すのも効果的です。
営業のノルマやKPIを過度に意識しすぎると、ストレスが増えて退職を考える理由になりやすいです。
目標の設定を調整するだけでも、業務の負担感を大きく減らせます。
行動量や目標を見直す方法は、以下のとおりです。
- ノルマを細かく分解して日・週ごとに管理する
- 月単位で未達でも、年間の成果を基準にすれば評価につながる
- 「毎月必ず達成」という固定観念を見直し、柔軟に営業活動を組み立てる
- ノルマはあくまで評価の一要素と捉え、会社が重視する最終成果に集中する
目標を調整すると、辞めるしかないと考える状況から抜け出し、営業を前向きに続けやすくなります。
転職を急ぐ前に、自分で改善できるポイントを探るのもキャリア形成に役立つでしょう。
信頼できる相談相手を社内外に持つ
人材営業の仕事で辞めたいと感じたときは、社内外に信頼できる相談相手を持つことが重要です。
成果が出ない原因や退職につながる悩みは、自分一人の努力だけでは解決できないケースがあります。
相談相手を持つメリットは、以下のとおりです。
- 上司に相談すれば具体的な営業方法や改善策が得られることもある
- 同僚や社外の知人など、複数の相談先を持つことで視点が広がる
- アドバイスがなくても、話を聞いてもらうだけで気持ちが軽くなる
しかし、必ずしも適切な助言が得られるとは限らないため、複数の相談先を持つのが望ましいでしょう。
一人で抱え込むと退職を早める理由になりかねません。
会社の中だけでなく、社外の人脈も含めて相談できる環境を整えるのが、営業を前向きに続けるための支えになります。
\人材業界のプロがキャリア相談/
人材営業を辞めた後に選べるキャリアパス
人材営業を辞めた後も、そこで培った営業力やコミュニケーション力は強みとして活かせるでしょう。
ここでは、人材営業経験を土台に次のキャリアへ進むための代表的な選択肢を紹介します。
他業界の営業職にキャリアチェンジする
人材営業を辞めた後は、他業界の営業職へ転職するのが有力なキャリアパスの一つです。
人材業界で培った営業力やコミュニケーション力は、業界を問わず企業に求められるでしょう。
例えば、人材派遣の仕事では無形商材を扱うため、自然とヒアリング力や提案力、問題解決力が磨かれます。
また、厳しい目標を乗り越えて培った忍耐力や粘り強さも、営業の世界で高く評価されやすい特性です。
多くの業界では専門知識よりも営業力や調整力が重視される傾向があるため、人材営業の経験はそのまま強みとして活かせます。
加えて、離職率が高いといわれる人材業界で成果を出した実績は、転職市場においてアドバンテージになりやすいでしょう。
人材営業を退職した後に他業界で営業職へキャリアチェンジするのは、実務経験を強みにできる現実的で将来性のある選択肢です。
人事・採用担当
人材営業を辞めた後のキャリアとして、人事・採用担当への転職は相性が良い選択肢です。
人材営業で培った「人と企業をつなぐ」経験やコミュニケーション能力は、会社の採用業務にそのまま活かせます。
実際に、人事・採用担当は自社の採用課題を解決する役割を担うため、経営者の考えや業務内容を理解する力が必要です。
日々企業と人材を結びつけてきた営業経験と共通しています。
また、候補者の意図を汲み取り言語化する力や、高いホスピタリティは、面接や応募者対応の場面で大きな強みになるでしょう。
人材営業で得た経験を基盤にすれば、人事・採用担当としてもスムーズに活躍できます。
コンサルティング業界
人材営業を辞めた後の転職先として、コンサルティング業界はキャリアアップを狙える選択肢です。
営業で培ったニーズ把握力や提案力は、企業の課題解決を行うコンサルタント業務と親和性があります。
コンサルティング業界は、高度な問題解決力を必要とする挑戦的な仕事です。
多業界の案件に関われるため広い知見を得られるため、人材業界で身につけた「課題を聞き出し、提案する力」はそのまま活かせます。
一方で、領域によっては専門知識や資格が必要で、入社前からの学習が求められる点には注意が必要です。
高収入ややりがいが期待できる反面、長時間労働やワークライフバランスに課題が生じやすい傾向もあります。
人材営業からの転職で得た経験は、コンサルティング業界で強みになりやすく、キャリア形成の幅を広げられるでしょう。
こちらも併せてチェック!
コンサル業界の転職エージェント一覧
IT・SaaS業界
人材営業を辞めた後の転職先として、IT・SaaS業界は成長性が高く、キャリアアップの選択肢として魅力的です。
IT・SaaS業界は人材需要が大きく、営業やコミュニケーション能力を活かしやすく、今後のキャリア形成に直結します。
例えば、人材派遣営業で培った提案力や調整力は、ITサービスやSaaS製品の販売、プロジェクトマネジメントにそのまま応用できます。
また、デジタル人材紹介など、人材業界とIT業界が融合する分野では、両方の経験を持つ人が強く求められているのです。
未経験歓迎の案件も多いため、入社後に知識を学ぶ姿勢や柔軟性をアピールすれば、採用企業に好印象を与えられるでしょう。
IT・SaaS業界は成長を続ける分野であり、人材業界での経験を活かしながら新しいキャリアを築ける可能性が高いです。
こちらも併せてチェック!
IT業界の転職エージェントおすすめ一覧
人材営業からのおすすめ転職先をさらに詳しく解説
人材営業で培ったスキルの転職先での活かし方
人材営業の仕事を通じて得られるスキルは、単なる営業力にとどまりません。
ここでは、それぞれのスキルがどのように新しい職場で活かせるかを解説します。
ヒアリング力を活かして顧客の課題解決につなげる
人材営業で培ったヒアリング力は、転職後もあらゆる業界・職種で即戦力になり、顧客の課題解決に直結します。
単に話を聞くだけでなく、共感と安心感を与えながら本音を引き出すと、表面化していないニーズまで把握できるためです。
ヒアリング力を活かせる場面は、以下のとおりです。
- 質問設計で相手の本音を引き出し、潜在的な課題を発見できる
- 共感的な対応で安心感を与え、顧客との信頼関係を構築できる
- 要望を正確に言語化し、課題に即した提案につなげられる
- 人材紹介で培った相談対応力を、IT・SaaS営業やコンサルにも応用できる
- 丁寧なヒアリングが継続取引や顧客紹介などの成果につながる
人材営業で培ったヒアリング力は、どの業界でも通用するスキルとして高く評価されます。
コミュニケーション力を武器に円滑な人間関係を築く
営業や人材業界で培ったコミュニケーション力は、転職先でもどの職種・業界においても高く評価されます。
コミュニケーション力は、社内の人間関係から取引先の企業とのやり取りまで、幅広い場面で信頼関係を築く基盤になるためです。
実際に活かせるシーンは、以下のとおりです。
- どの職場・業種でも必須スキルとして評価されやすい
- 初対面の相手ともスムーズに会話を進められる
- 自分の考えを分かりやすく伝える表現力がある
- 相手の感情や反応を読み取り、柔軟に対応できる
- 職場内の人間関係や商談でも、信頼構築に直結する
営業や人材業界で磨いたコミュニケーション力は、転職後も幅広い分野で役立ち、高い評価につながるでしょう。
多業種対応で磨いた適応力で即戦力になる
人材営業の経験で培った「適応力」は、転職後のキャリアでも即戦力として高く評価されるでしょう。
営業職は、IT・飲食・医療・メーカーなど幅広い業界の企業と関わるため、自然と多様な業界知識や専門用語を理解する力が身につきます。
適応力が発揮できる具体例は、以下のとおりです。
- ITやWeb業界など変化の速い分野でも、即戦力として期待されやすい
- 業界ごとの特徴を理解しているため、顧客対応や提案の質が高い
- 新しい環境でも短期間で業務に順応し、成果につなげられる
多業種で培った適応力は、新しい環境に強い人材として評価されやすく、転職市場でのアピールにつながります。
厳しい環境で鍛えた忍耐力を強みにできる
人材営業の仕事で培った忍耐力は、転職活動や新しいキャリアにおいて大きな評価材料となります。
営業職は長時間労働や多くの業務に直面することが多く、退職を考える人も少なくありません。
しかし、その厳しい環境を乗り越えた経験は、どの会社や業界でも通用する強いメンタルと継続力につながります。
忍耐力が評価される具体例は、以下のとおりです。
- ノルマや長時間労働を乗り越えた経験は粘り強さにつながる
- 長期案件の対応で持久力を養える
- 働き方改革の職場では余裕を持って成果を出せる
- 難しい環境でも前向きに成果を出す姿勢が評価される
厳しい環境で鍛えた忍耐力は、逆境でも成果を出せる人材として企業から信頼を得やすく、転職市場で強い武器となります。
人材営業を辞めたいと感じたときのよくある疑問
ここでは、人材営業を辞めたいと感じたときに抱きやすい疑問に回答します。
人材営業に「向いてる人」と「向いてない人」の違いはなんですか?
人材営業に向いている人は、能動的に学びながら信頼関係を築き、変化を楽しめるタイプです。
一方、受け身で柔軟さに欠ける人は相性が合いにくい傾向があります。
営業の仕事は常に新しい知識や情報が求められ、求職者や企業との関係構築、状況に応じた柔軟な対応が欠かせません。
具体例は、以下のとおりです。
- 受け身で自ら学ぶ姿勢が弱い
- 人間関係や変化への対応が苦手
- 淡々とした業務を好み、対人中心の仕事を負担に感じやすい
- プレッシャーやトラブルに動揺しやすい
自分が「向いている人」「向いていない人」のどちらに当てはまるかを見極めるのが、キャリアの方向性を考える第一歩となるでしょう。
こちらも併せてチェック!
人材営業に向いている人の特徴をさらに詳しく解説
人材営業を辞めたいと感じたら、どこに相談すべき?
人材営業を辞めたいと感じたら、転職エージェントに相談してみるのもおすすめです。
転職エージェントは、営業経験やスキルを踏まえて適した転職先を紹介し、キャリア形成を客観的にサポートしてくれます。
具体例は、以下のとおりです。
- 経験・スキルをもとに最適な転職先を紹介
- プロの視点で強みや選択肢を提案
- 給与や条件の交渉を代行
- 入社後のフォローで安心
一人で悩むよりも、専門的なアドバイスを受けると、キャリアの可能性を広げながらスムーズに転職活動を進められます。
どのエージェントに相談すればいいか迷っている方はこちらをチェック
人材業界の転職エージェントおすすめ一覧
人材営業を辞めたいときは状況を整理して前向きなキャリア選択につなげよう
人材営業を辞めたいと感じたときこそ、自分の「理由」や「状況」を整理するのが大切です。
ノルマや営業手法などに悩む場面もありますが、その経験は多くの場で通用するスキルにつながります。
転職を考える際は、焦らず自分の強みと将来像を見つめ直しましょう。
「ひとキャリ」では、人材営業からのキャリアチェンジを考える方に向けて、無料相談や非公開求人の紹介をおこなっています。
安心して次の一歩を踏み出せるようサポートしていますので、前向きなキャリア選択にぜひご活用ください。
\30秒で申し込み完了!/