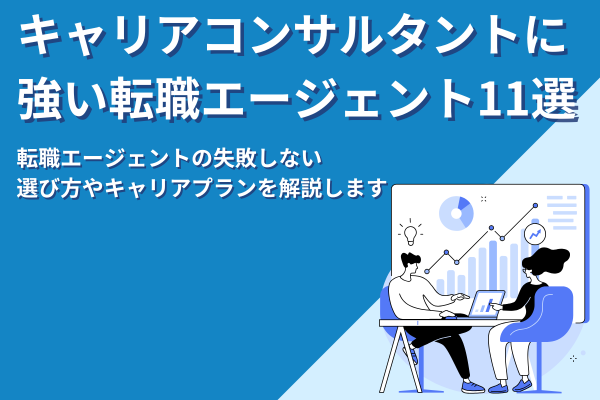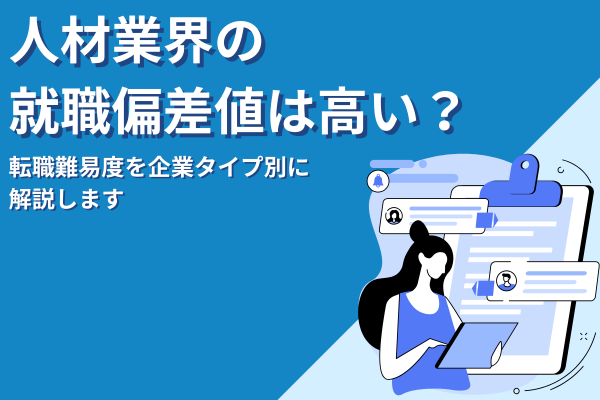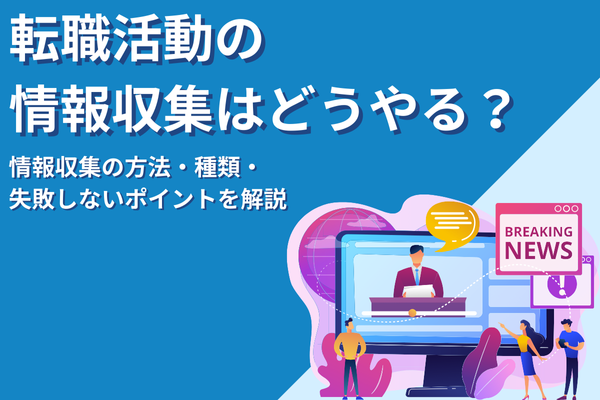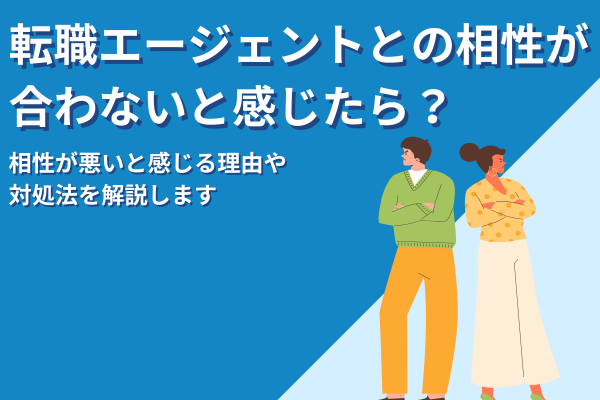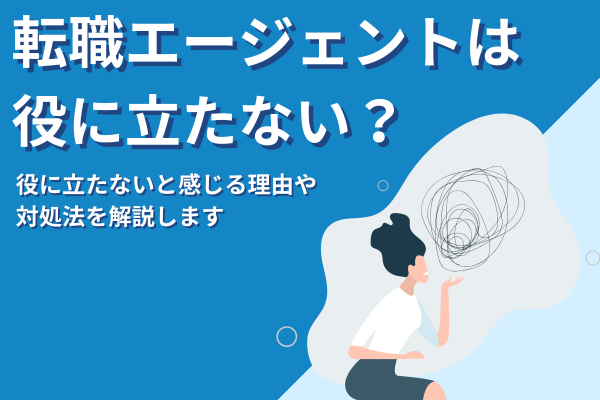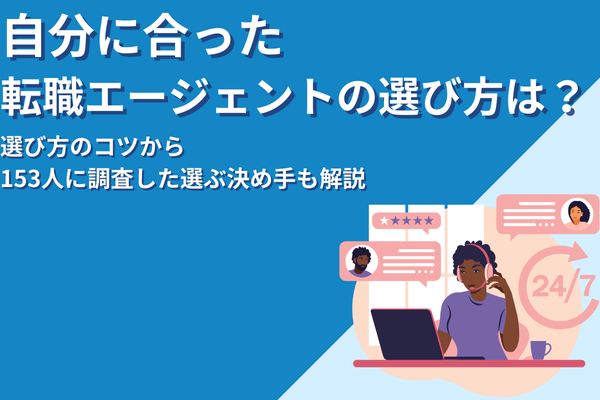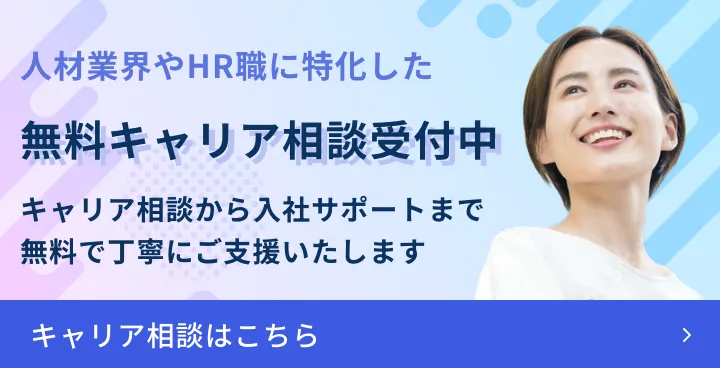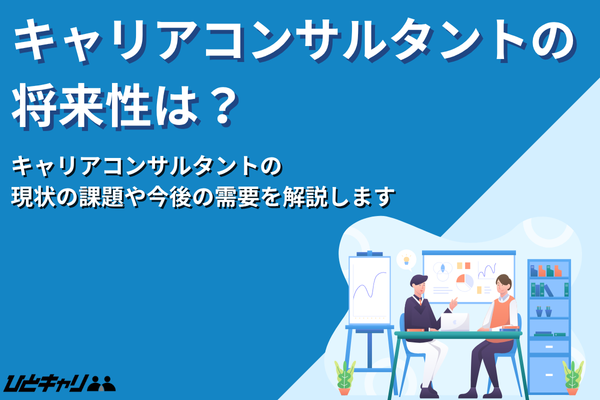
公開日: 2025.07.16
キャリアコンサルタントに将来性はある?現状と課題・今後の需要を解説
「キャリアコンサルタントって、将来性はあるの?」
「キャリアコンサルタントを今から目指しても遅くない?今後需要はある?」
そんな不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
キャリアコンサルタントは、働く人のキャリア形成を支援する国家資格者です。
近年では、企業内の相談体制の整備や教育現場への導入、労働政策との連携など、活躍のフィールドが広がりつつあります。
この記事では、キャリアコンサルタントの現状と課題、将来性についてわかりやすく解説します。
「キャリア支援に興味はあるけど、実際どうなのか不安…」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
キャリアコンサルタントとして働きたい方は、人材業界特化の転職エージェント「ひとキャリ」の利用がおすすめです。
キャリアコンサルタントとしてのキャリアプランや求人を紹介します。
また、人材業界の知見を活かした面接対策で、選考通過率を大幅にアップできます。
気になる方は1分で申し込み可能な無料相談から始めてください。
\キャリアコンサルタント求人を紹介/
目次
キャリアコンサルタントに将来性・今後の需要はある?
キャリアコンサルタントの将来性は、これまで以上に注目されています。
ここでは、キャリアコンサルタントの「今後の需要」と「将来性」について、4つの視点からわかりやすく解説します。
人員不足が進み、キャリア支援の重要性が高まっている
キャリアコンサルタントの役割は、今後さらに重要性を増すと見込まれています。
社会全体で働き方の多様化が進み、キャリアに対する価値観も変化しているためです。
その中で、個人の状況に合わせたキャリア支援を提供できる専門人材の需要が高まっています。
厚生労働省の調査によると、以下のような状況が指摘されています。
- 急激な社会変化の中で、個人のキャリア自立を支援する力が求められている
- 副業や転職の増加により、個別に寄り添う支援の重要性が高まっている
- 登録者の高齢化が進み、30〜40代の人材不足が課題となっている
こうした背景から、キャリア支援のニーズは今後さらに拡大し、キャリアコンサルタントの将来性と必要性は高まっていくといえるでしょう。
参考:厚生労働省「経済社会情勢の変化に対応したキャリアコンサルティングの実現に向けて」
働き方の多様化で支援ニーズが拡大している
社会の変化にともない、キャリアコンサルタントへの支援ニーズは今後さらに拡大していきます。
DXの加速や副業・リモートワークの普及など、働き方が多様化する中で、労働者には自律的・継続的なキャリア形成やリスキリングが求められるようになっているためです。
厚生労働省の調査によると、以下のような状況が示されています。
- DXや社会の変化により、労働市場データの活用やリスキリング支援など、専門的なスキルが求められている
- 職業人生の長期化により、年代や状況に応じたキャリア支援の重要性が増している
- 法制度や政策の後押しにより、企業でのキャリアコンサルティング導入も進んでいる
多様な働き方や学び直しへの対応が求められる今、キャリア支援のプロフェッショナルであるキャリアコンサルタントの存在は、今後さらに重要性を増していくと考えられます。
参考:厚生労働省「経済社会情勢の変化に対応したキャリアコンサルティングの実現に向けて」
企業の相談体制整備で活躍の場が広がっている
企業内におけるキャリア支援体制の整備が進み、キャリアコンサルタントの活躍の場が広がりつつあります。
働き方改革や人材育成の観点から、企業は従業員のキャリア形成を支援する責任を強く意識するようになってきているためです。
厚生労働省の報告では以下の点が挙げられています。
- 大企業ではキャリア相談室の設置や社内の資格保有者の活用が進んでいる
- 中小企業でも外部コンサルタントによる支援導入のニーズが高まっている
- セルフ・キャリアドック制度の普及により、制度的に相談機会を整備する企業が増えている
キャリアコンサルタントは企業内外を問わず、相談支援や制度運用の専門職としての役割が拡大しており、今後も活躍の場が広がると考えられます。
参考:厚生労働省「働く環境の変化に対応できるキャリアコンサルタントに関する報告書」
AIでは代替できない寄り添う力が求められている
キャリアコンサルタントには、AIでは代替できない「共感力」や「寄り添う姿勢」が求められています。
AIは情報の整理や分析には優れているものの、相談者の不安や迷いに対して感情面から関わることはできないためです。
個人の内面に深く踏み込み、価値観や背景に寄り添った支援をおこなうには、人間ならではの対話力が必要でしょう。
多様な生き方や働き方が広がる中で、相談者自身が納得して行動できるよう導く支援は、キャリアコンサルタントだからこそ担える役割といえます。
AIが進化を遂げる一方で、キャリアコンサルタントに求められる「人間らしさ」はむしろ重要性を増していくと考えられます。
感情に寄り添い、対話を通じて支えるキャリア支援の価値は、今後さらに高まっていくでしょう。
キャリアコンサルタントの市場規模で見る将来性の有無
キャリアコンサルタントは、市場規模が拡大しており、将来性の高い国家資格です。
国による制度化により資格の信頼性が高まり、支援効果も実証されているため、企業や自治体での導入が年々進んでいます。
以下は、キャリアコンサルタントに関するデータです。
| 観点 | 動向 |
|---|---|
| 制度創設の背景 | 2016年に国家資格として位置づけられ、資格保有者の質・役割が制度的に保障されるように |
| 登録者数の推移 | 制度創設から7年で約6.6万人が「キャリアコンサルタント名簿」に登録 |
| 資格合格者数 | 累計10万人以上が国家試験に合格 |
| 導入状況 | 守秘義務や信用失墜行為の禁止が明文化され、企業・自治体での導入が拡大中 |
| 支援効果 | 相談経験者の6割が「職業生活に変化があった」と実感 |
| 支援 ニーズ | 「今後も相談したい」48%、「満足度」54.8%(未経験者の33.9%より高い) |
国家資格として制度化されたことにより、信頼性と効果が広く認められており、キャリアコンサルタントは今後もニーズが拡大していく分野といえるでしょう。
参考:厚生労働省「キャリアコンサルタント登録制度等に関する検討会報告書」、労働政策研究報告書No.233「キャリアコンサルティングの有用度及びニーズに関する調査」
キャリアコンサルタント業界の現状の課題は?
キャリアコンサルタントの需要が高まる一方で、現場ではさまざまな課題も浮き彫りになっています。
制度の整備や資格保有者の増加は進んでいるものの、実際の活用や現場への定着にはまだ壁があるのが現状です。
ここでは、キャリアコンサルタント業界が抱える主な課題を5つの観点から整理してみましょう。
制度導入は進むも、活用が限定的で定着しにくい
企業におけるキャリアコンサルティング制度の導入は進んでいるものの、現場での活用は限定的で、定着には至っていないのが現状です。
制度自体は整いつつありますが、「相談の効果が見えにくい」「相談時間が確保できない」などの運用上の課題が多く、現場での実施が形骸化しやすい傾向があります。
厚生労働省の調査による具体的な現状は、以下のとおりです。
- キャリアコンサルティングを導入している企業は約40%にとどまる
- 導入企業の43%が「効果が見えにくい」と感じている
- 36%が「相談の時間を確保するのが難しい」と回答
- 相談件数が少ない(35%)、社内人材の育成が困難(約29%)なども定着の妨げに
また、社内に相談対応できる人材の育成や、外部依頼にかかるコストも障壁となっています。
制度面では一定の整備が進んでいても、現場での実効性や活用度が十分とは言えません。
今後の定着には効果の「見える化」と継続的な実施を支える体制づくりが重要です。
参考:厚生労働省「キャリアコンサルティング・ キャリアコンサルタントの現状」
実践機会の不足とスキル維持の難しさ
キャリアコンサルタントは、実践の場が限られていることがスキル維持・向上の大きな壁となっています。
具体的な背景は、以下のとおりです。
- キャリアコンサルタントの主な活動場所は企業(40.2%)、公共機関(23.8%)、教育機関(20.2%)などに分散している
- 地域や機関ごとに相談ニーズや件数にばらつきがあり、継続的な実践の機会が確保しにくい
- 5年ごとの登録更新制度では「知識講習8時間」「技能講習30時間」が義務づけられている
- 現場経験が乏しい状態での講習受講では、実務に生かしづらいという課題も見られる
スキルの維持や専門性の強化には、知識の習得だけでなく、定期的かつ安定した実践の積み重ねが不可欠です。
資格制度の整備と並行して、現場経験を得やすい仕組みづくりが求められています。
参考:厚生労働省「キャリアコンサルティング・ キャリアコンサルタントの現状」
対応人材・時間の不足
キャリアコンサルティングを制度として導入しても、現場では人と時間が足りず、十分に機能していないケースが多く見られます。
実際に相談体制を整えていても、相談希望者が少なかったり、相談時間が確保できなかったりするなど、運用面での課題が顕在化している現状です。
厚生労働省の調査で以下のように課題が挙げられています。
- 企業のキャリア相談体制において、「効果が見えにくい」「人材や時間が足りない」などの運用課題が多数報告されている
- 外部のキャリアコンサルタントに依頼するには費用がかさみ、継続的な実施が難しい
- 社内で対応できる人材の確保・育成も容易ではなく、他業務との兼務などで十分な対応ができていない
制度の枠組みだけでなく、実際に相談を機能させるための「人的・時間的リソース」の確保が今後の重要課題です。
現場で無理なく運用できる仕組みづくりが急がれています。
参考:厚生労働省「キャリアコンサルティング・ キャリアコンサルタントの現状」
相談内容の複雑化・高度化
キャリアコンサルティングの現場では、相談内容の質・難易度が年々高まっており、対応の難しさが増しています。
相談者の背景や課題が複雑化しており、高度な対応力が求められるでしょう。
具体的には、以下のとおりです。
- キャリア相談のテーマは、若年層だけでなく中高年層の再就職や、精神的な問題を含むケースなどに拡大している
- 相談の高度化に対し、十分な専門性を持ったキャリアコンサルタントが不足しており、現場の対応力に限界がある
これからのキャリア支援には、幅広いテーマに対応できる専門性と実践力が求められます。
相談の複雑化に対応するためにも、人材育成と支援体制の強化が欠かせません。
参考:厚生労働省「キャリアコンサルティング・ キャリアコンサルタントの現状」
キャリア支援制度の浸透不足
制度自体は整ってきているものの、企業や働く人への認知が進まず、十分に活用されていないのが現状です。
働き手のキャリア自立を支える制度として「セルフ・キャリアドック」などが用意されていますが、実際に導入・活用できている企業は限られています。
具体的な背景や事例は、以下のとおりです。
- 全国41か所に相談窓口が設置され、平日夜間や土曜日も対応しているにもかかわらず、制度自体を知らない人が多い
- 「セルフ・キャリアドック」は制度として整備されているが、導入企業は限られる
- 導入した企業では効果も出ているものの、その成功事例が他に広がっていない
せっかく制度が整備されていても、知られていなければ活用されません。
今後は、制度の存在と効果を広く発信し、企業が導入しやすい環境づくりを進めることが重要です。
参考:厚生労働省「キャリアコンサルティング・ キャリアコンサルタントの現状」
キャリアコンサルタントがやめとけと言われる理由
キャリア支援の専門職として注目されるキャリアコンサルタントですが、「やめとけ」などの声があがることもあります。
ここでは「やめとけ」と言われる理由について、代表的な声を5つに整理してご紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
資格だけでは仕事につながりにくい
キャリアコンサルタントの資格を持っていても、それだけで仕事が決まるとは限りません。
実際の採用現場では、資格よりも相談対応などの実務経験が重視されるケースが多いためです。
具体的な理由は、以下が挙げられます。
- 求人サイトで「キャリアコンサルタント」と検索しても、資格不要の人材紹介職や営業職が多く含まれる
- 資格保有が応募条件となっている求人は一部に限られる
- 実務で求められるのは、履歴書添削・傾聴・面談進行などのスキル
- 国家資格キャリアコンサルタント試験に合格しても、企業内での相談実績が求められるケースが多い
資格を取れば仕事に直結すると期待しすぎるのは危険です。
資格取得前に、実務経験の積み方や求人の実情を確認しておくことをおすすめします。
非正規雇用が多く、安定した収入が得にくい
キャリアコンサルタントは、正社員比率が低く、安定収入を得にくい働き方になる傾向があります。
多くの現場で非正規雇用や業務委託が主流となっており、雇用形態や働く時間が不安定なためです。
キャリアコンサルタントの働き方の具体例は、以下が挙げられます。
- 正社員として働く人は約4割、残りは非常勤・フリーランス・ボランティアなどが多数
- 自治体の窓口や大学などでは、1年更新の契約が基本で、継続雇用は保証されない
- 相談業務は繁忙期に偏りがあり、収入が月ごとに変動しやすい
- 複数の現場を掛け持ちしないと生活が成り立たず、移動・事務作業の負担も増大
キャリアコンサルタントの働き方は柔軟な反面、安定を求める人にとっては不安定さや収入面のリスクを感じやすいといえます。
働くスタイルの実態を理解したうえで、自分に合ったキャリア設計を考えるのが大切です。
参考:厚生労働省「キャリアコンサルティング・ キャリアコンサルタントの現状」
ノルマや成果目標にプレッシャーを感じやすい
キャリアコンサルタントの仕事は、ノルマや成果目標に強いプレッシャーを感じやすい職種です。
多くの職場では「成果=評価や報酬」に直結しており、常に数字や結果を求められます。
とくに転職支援や人材紹介の分野では、求職者と企業の双方に満足してもらう必要があり、その調整力や成果が厳しく見られます。
実際に、成果が出なければ評価されづらく、目標未達によって契約更新が難しくなる場合もあるでしょう。
また、限られた相談時間や人員の中で、日々複数の案件に対応する必要があるため、精神的な負担が蓄積しやすいのが実情です。
結果重視の職場環境においては、数字や成果に対するプレッシャーに耐える力が求められるでしょう。
資格維持に費用と手間がかかる
キャリアコンサルタントの資格は、取得後も「維持のための費用と時間」がかかるため、継続が負担になるケースも少なくありません。
資格を維持するには、5年ごとに講習の受講と更新手続きが義務づけられており、働きながらの対応が難しい場面も多いためです。
働きながらの時間確保や費用面での負担が、特に個人で活動している方にとっては大きなハードルになります。
資格維持にかかる具体的な負担は、以下のとおりです。
- 更新には「知識講習8時間+技能講習30時間」の受講が必須
- 講習費用は合計で3〜5万円程度が相場
- フリーランスや非常勤の場合、費用を全額自己負担するケースが多い
- 実際の更新率は令和3年度で69.0%、令和4年度で70.6%にとどまり、約3割が更新できていない
キャリアコンサルタント資格は取得すれば終わりではなく、働き続けるためには継続的な自己投資とスケジュール管理が欠かせません。
参考:厚生労働省「キャリアコンサルティング・ キャリアコンサルタントの現状」
業務負担が重く、専門業務に集中しにくい
キャリアコンサルタントの仕事は、相談業務だけではありません。
事務作業や運営サポートなど多岐にわたる業務を抱えると、肝心のキャリア支援に十分な時間を割けないのが現状です。
とくに大学や教育機関では、学生対応に加えて、就職ガイダンスの運営や求人票の管理、報告書作成などの事務業務が多く、負担が大きくなってしまうでしょう。
業務過多によって専門性を発揮しづらい具体例としては、以下のようなものがあります。
- 就職イベントや説明会の準備・運営に多くの時間が取られる
- 求人票の整理や学生対応に追われ、面談の時間が後回しになる
- 報告書の作成やシステムへのデータ入力など、事務作業の比重が高い
キャリア支援の専門職としてのスキルや経験を深めるには、相談業務に集中できる環境整備が欠かせません。
将来性のあるキャリアコンサルタントの特徴
キャリアコンサルタントとして長く活躍していくには、単に資格を持っているだけでなく、現場のニーズや社会の変化に柔軟に対応できる力が欠かせません。
ここでは、将来性のあるキャリアコンサルタントに共通する特徴を4つの視点から解説します。
特化領域(中高年・女性支援・副業相談など)に強みがある
将来性のあるキャリアコンサルタントには、「特定分野に強みがあること」が求められます。
相談者のニーズが多様化するなかで、誰でも相談できる汎用性よりも、「この人なら安心して相談できる」と感じてもらえる専門性のほうが価値を示すことができるでしょう。
具体例は、以下のとおりです。
- 人事経験を活かし企業向けに特化すると、経営層からの信頼を得やすい
- 中高年支援に特化すると、年齢特有の悩みに的確に対応できる
- 副業や兼業に詳しいと、柔軟な働き方を求める人をサポートできる
- 幅広く対応するより、「この分野に強い人」と認識されるほうが依頼が続きやすい
特定領域での知見や経験があると、信頼されやすくなり、マッチングの精度も高まります。
キャリアコンサルタントとしての将来性を高めるには、自分の専門性を明確に打ち出すのが重要です。
専門外の相談にも落ち着いて対応し、他機関と連携できる
信頼されるキャリアコンサルタントには、専門外の相談にも冷静に対応し、必要に応じて他機関と連携する力が求められます。
キャリア相談では、就職支援だけでなく「メンタルヘルス」「職場の人間関係」など複雑な課題に直面する場合があるためです。
具体的には、以下のような連携が必要でしょう。
- メンタル不調が見られる相談者には、専門機関の受診を促す
- 発達障害の可能性がある場合、支援機関と連携して対応
- 職場の人間関係の課題は、人事や産業医と協力して解決を図る
自分の限界を理解し、他職種と連携して支援する姿勢が、キャリアコンサルタントとしての信頼を高めます。
人との対話力とITリテラシーを両立できる
これからのキャリアコンサルタントには、相談者の信頼を得る「対話力」と、AI・デジタル技術を理解し活用できる「ITリテラシー」の両立が不可欠です。
近年は、相談者の悩みを丁寧に引き出す力に加え、生成AIや機械学習、自然言語処理などのデジタル技術を理解し、支援に活かすスキルが求められています。
たとえば以下のようなスキルがある人材は、活躍の場を広げていけるでしょう。
- AIやデータ分析を活用し、課題解決型のキャリア相談ができる
- 難しい技術情報をわかりやすく伝え、相談者との信頼関係を築ける
- 共感的な対話をベースに、戦略的な支援を展開できる
単なるシステム理解ではなく、「人との信頼関係を築く力」と「技術を伝える力」を両立できるキャリアコンサルタントこそ、今後さらに活躍の場を広げていくでしょう。
実践を通じて学び続け、地域・業界のニーズを捉えている
キャリアコンサルタントとして信頼され続けるためには、現場のニーズに合わせて学び続ける姿勢が欠かせません。
とくに地域や業界特有の課題に対応するには、常にスキルをアップデートすることが重要です。
キャリアコンサルタントは5年ごとに更新講習を受ける義務があり、その学びが支援力の向上につながります。
たとえば以下のような取り組みによって、実践的な成長が可能です。
- 実務で感じたスキルの不足を、講習でピンポイントに補う
- 地域や業界の課題に応じた支援法を習得し、即現場に活かす
- キャリアコンサルティング技能士(1級・2級)の取得により専門性をさらに深める
講習のテーマは多岐にわたるため、自分の支援対象や専門領域に合った内容を計画的に選択できます。
現場の実感に根ざした学びを積み重ねると、信頼されるキャリア支援につながるでしょう。
将来性のないキャリアコンサルタントの特徴
キャリアコンサルタントとしての将来性は、資格の有無だけではなく、日々の姿勢や関わり方によって大きく左右されます。
ここでは、キャリアコンサルタントとしての信頼や役割を果たせなくなる可能性のある特徴を解説しているので、ぜひ参考にしてください。
相談者の価値観を尊重できない
相談者の価値観を尊重できないキャリアコンサルタントは、信頼を得にくく、適切な支援ができなくなります。
キャリア支援では、働き方や人生観など、相談者ごとに異なる価値観が強く影響するためです。
一方的な考えを押しつけてしまうと、相談者の自己決定を妨げてしまいかねません。
具体例は、以下のとおりです。
- 副業を希望する相談者に「正社員で安定すべき」と決めつける
- 転職を考えている人に「もう少し今の職場で頑張るべき」と一方的に促す
- 育児と両立した働き方を望む人に、フルタイム勤務を勧める
- 自営業やフリーランス志望の相談者に対し、否定的な態度を示す
信頼されるキャリアコンサルタントには、相談者の背景や考えを丁寧に受け止め、価値観に寄り添った柔軟な提案力が求められます。
時代の変化や多様な働き方を踏まえた支援ができなければ、本質的なキャリア支援とはいえないでしょう。
情報の更新を怠り、時代に合った支援ができない
キャリアコンサルタントが情報の更新を怠ると、変化の早い時代に対応できず、相談者からの信頼を失いかねません。
DX化や副業解禁、キャリアの複線化が進むなかで、支援に必要な知識も大きく変化しています。
古い価値観や知識のままでは、相談者の課題に応えられません。
具体例は、以下のとおりです。
- 「正社員が安定だから」と副業希望者を否定してしまう
- リスキリングの相談に対して、最新のスキル需要や学習方法を把握していない
- フリーランス志望の相談者に対して、業界動向や契約面の知識が乏しい
- DX化が進む業界への転職支援で、必要なITスキルや学習ルートを説明できない
信頼されるキャリアコンサルタントであり続けるには、自身も常に学び続ける姿勢が不可欠です。
情報をアップデートし、時代に即した提案ができる力こそが、支援の質を左右します。
相談者への関心が乏しく、関係性を築けない
キャリアコンサルタントは、相談者に関心を持ち、限られた時間で信頼関係を築く力は欠かせません。
キャリアコンサルティングの時間は限られており、相談者の話に真摯に耳を傾け、共感する姿勢がなければ、信頼関係は築けないでしょう。
具体例は、以下のとおりです。
- 相手に興味を持てず表面的な対応になると、相談者は本音を話しづらくなる
- 「人は人、自分は自分」といったスタンスでは、寄り添った支援が難しくなる
- 初対面でも関係性を築ける聴く力・共感力が求められる
人への関心が薄いままでは、キャリア支援の土台となる信頼関係が築けません。
対話力と共感力は、キャリアコンサルタントにとって不可欠な資質といえるでしょう。
倫理・法への配慮が欠けている
キャリアコンサルタントには、個人情報の取り扱いや法令遵守といった倫理的・法的な配慮が欠かせません。
支援現場ではプライバシー性の高い情報を扱うことが多く、信頼を守るには高い倫理観と知識が必要です。
対応を誤れば、信頼を失うだけでなく、トラブルに発展するリスクもあります。
具体例は、以下のとおりです。
- 相談内容や個人情報を不用意に他者へ共有してしまう
- 利用目的や保管方法が不明確なまま情報を扱う
- 契約や雇用に関する法的知識が不足しており、誤った助言をしてしまう
信頼されるキャリアコンサルタントになるためには、倫理・法令への意識を常に持ち、支援の一つひとつに慎重さと責任感をもって臨む姿勢が欠かせません。
キャリアコンサルタントになるには?
キャリアコンサルタントになるには、所定のステップを順を追ってクリアする必要があります。
ここでは、キャリアコンサルタントとして正式に活動を始めるまでの流れを、厚生労働省に記載の4つのステップに分けてわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
ステップ1:受験資格を確認する
キャリアコンサルタントになるには、まず自分が国家試験の受験資格を満たしているかを確認する必要があります。
国家資格キャリアコンサルタントは、厚生労働大臣が定める条件をクリアした人のみが受験できる制度です。
講習の受講や実務経験など、いくつかのパターンがあるため、自分に最適なルートを把握しておくことが重要です。
1.養成講習ルート(最も一般的)
- 厚生労働大臣認定のキャリアコンサルタント養成講習を修了する方法が一般的
- 対面・オンライン講座のいずれかを選べ、講習機関により費用やカリキュラムが異なる
2.実務経験ルート(相談業務3年以上)
- 「職業選択」「職業生活設計」「職業能力開発」のいずれかに関する個別相談業務を、1対1または6人以下の規模で3年以上経験している場合
- 講習なしで受験可能(証明書提出が必要)
3.技能検定ルート(学科・実技の一部免除)
技能検定キャリアコンサルティング職種の学科試験又は実技試験に合格した者
4.特例ルート(個別審査)
上記に準ずる実務経験や専門知識を持っていると認められた場合、個別審査を経て例外的に受験資格が認められることがある
自分がどのルートに該当するかを早めに確認すると、キャリアコンサルタント資格取得までの準備がスムーズになります。
ステップ2:国家試験に合格する
キャリアコンサルタントとして登録するには、国家試験の学科試験と実技試験の両方への合格が必要です。
国家資格として認められるためには、知識面と実務スキルの両方を備えていることが求められます。
試験はそれぞれ形式・配点・合格基準が明確に定められており、事前に把握しておくことで、効率的な対策ができます。
学科試験の概要
- 形式:マークシート式(四肢択一)
- 問題数・時間:50問/100分
- 合格基準:70点以上(100点満点)
- 受験料:8,900円
実技試験の概要
- 構成:論述+面接(ロールプレイ+口頭試問)
- 合格基準:150点満点中90点以上、かつ各項目で40%以上の得点が必要
- 時間:論述50分/面接20分(ロールプレイ15分+口頭試問5分)
- 受験料:29,900円
試験免除制度について
- すでに学科試験または実技試験のいずれかに合格している場合、その試験は免除対象となる
- 1級・2級キャリアコンサルティング技能検定の一部合格者も同様の免除が適用される
出題形式や合格基準を把握し、事前にしっかりと準備しておきましょう。
ステップ3:名簿登録をおこなう
キャリアコンサルタント試験に合格した後は、「キャリアコンサルタント名簿」へ登録すると、正式に国家資格キャリアコンサルタントとして活動可能です。
名簿登録は、法律で定められた必須の手続きであり、厚生労働大臣が指定する「キャリアコンサルタント登録センター」を通じておこないます。
具体的なステップは、以下のとおりです。
- 登録申請はWebマイページから開始
- 登録申請書一式と合格証の写しを登録センターへ郵送
- 登録免許税として9,000円(収入印紙)、登録手数料として8,000円(非課税)が必要
- 審査後に「キャリアコンサルタント登録証」を交付
- 登録証は申請から約2か月後に自宅へ郵送
- 一部合格証や経過措置証明書では登録不可(合格証の有効性に注意)
名簿登録の完了をもって、国家資格キャリアコンサルタントとして名乗り、正式にキャリア支援の実務に従事可能です。
ステップ4:定期的に更新講習を受ける
キャリアコンサルタントとして登録を継続するには、5年ごとに「更新講習(知識講習・技能講習)」を修了する必要があります。
国家資格キャリアコンサルタントには、社会の変化に対応できる最新の知識と実践力が求められます。
定期的な学びにより、支援の質を維持・向上させることが目的です。
講習内容は、以下のとおりです。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 知識講習 | 労働法、社会保障制度、労働市場の動向などを学ぶ(8時間以上) |
| 技能講習 | カウンセリングや意思決定支援など、実践的なスキルを強化(30時間以上) |
| 申請時期 | 登録証の有効期限満了日の90~30日前に申請 |
5年ごとの更新講習は、キャリア支援の専門家として必要なスキルと知識を保つために欠かせない制度といえるでしょう。
こちらの記事も併せてチェック!
キャリアコンサルタントの難易度を徹底解説
キャリアコンサルタントの将来性は行動次第で広がる
キャリアコンサルタントとして将来性を広げていくには、資格を取れば終わりではなく、自ら学び続ける姿勢と行動が欠かせません。
働き方や労働市場が急速に変化する今、どのような場面で誰を支援したいのか、どんな知識・経験を積みたいのかを考え、積極的にスキルを磨いていくことが求められています。
企業内での人材育成、学校での進路支援、自治体との連携など、キャリアコンサルタントが活躍できるフィールドは確実に広がっています。
社会からのニーズも高まっているからこそ「どんな支援ができるか」を言語化し、自分の強みを活かせる場所を見極めることが大切です。
「ひとキャリ」では、キャリア支援に携わりたい方に向けて、業界特化型の非公開求人を紹介しています。
無料のキャリア相談では、実務に詳しいプロのコンサルタントが、あなたの志向や希望に沿った活躍の場をご提案します。
「どんな働き方なら自分らしく成長できるか知りたい」と感じている方も、ぜひ一度ご相談ください。
\キャリアコンサルタント求人を紹介/
転職を考えている方はこちらも併せてチェック!
人材業界の転職エージェントおすすめ11選